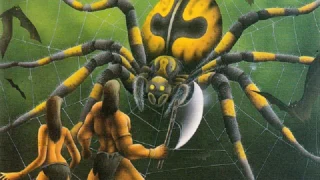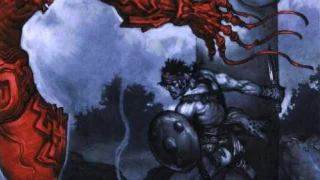本記事では、シミュレーションRPG『フェーダ』シリーズの魅力を徹底解説しています。初代『ジ・エンブレム・オブ・ジャスティス』からリメイク版、続編『ホワイト=サージ』まで、世界観・物語・称号や資源管理などの独自システム、種族や勢力の関係性を詳細に紹介し、未完のまま残された物語の余韻とシリーズ全体の特色をまとめています。
シリーズの概要

『フェーダ』シリーズは、マックス・エンターテイメントが開発し、やのまんから発売されたシミュレーションRPGで、スーパーファミコンの『フェーダ 〜 ジ・エンブレム・オブ・ジャスティス』、そのセガサターン版リメイク、そしてプレイステーションの『フェーダ2 ホワイト=サージ・ザ・プラトゥーン』から構成されます。舞台は種族と帝国が対立する架空世界で、革命と内乱を背景に物語が展開します。初代では称号システムによってプレイヤーの行動がLAWからCHAOSへと評価され、仲間や結末が変化する独特の分岐性を持ち、捕虜救出などの要素も戦略に絡みます。続編『WSP』では固定部隊制と資源管理が重視され、兵装変更や野戦病院システム、部隊ポイント(OPM)による運営など、指揮官的判断を強く要求する仕組みが導入されました。種族間の確執や帝国と解放軍の攻防、前作キャラクターの再登場などが物語に厚みを与え、未完のまま残された伏線が続編への期待を生んでいます。シリーズ全体を通して、戦場での一手が倫理や歴史の重さに直結することが最大の魅力です。
シリーズの魅力
種族と政治が絡み合う“生きた世界観”

舞台となるミルドラス=ガルズは、ドラゴニュートやグルナレイム、ウルフリング、クラナス、セントール、アルシデア、マシンヘッドなど多様な種族が共存し、それぞれが誇りや偏見、利害を抱えています。長く続いたミレニアム・ナイトメア戦役の余燼、古代兵器「終焉の四賢者」による地形そのものの変容、帝国バルフォモーリアの支配構造、辺境スクーデリアでの圧政と解放戦線の台頭が、物語の背景に厚みを与えます。『EOJ』では種族間対立が露骨に描かれ、『WSP』では視点が広がり価値観の変化も見えてきます。敵・味方の単純な図式に閉じず、宗教的権威や元老院、総督と四提督、解放軍の思想家や軍師など、政治と思想のレイヤーが幾重にも重なるため、戦場での一手が世界の均衡に触れる手触りがあります。
作戦準備から撤収まで続く“戦術の呼吸”

キャンプでの編成・装備・補給、ミッションでの地点確保や護衛、籠城、敵将撃破などの多様な目標、戦闘後の帰還と次指令という流れが、軍事作戦の循環として一体化しています。『EOJ』では捕虜収容所の存在により、味方が倒れても救出作戦で取り戻せる余地があり、損害の扱いが戦略判断になります。『WSP』では戦闘不能者が野戦病院で軽傷・重傷に分類され、完治を待つか即応戦力を維持するかの選択が迫られます。さらに『WSP』は行動後の再移動が可能になり、前に出て撃ち、間合いを外すヒット&アウェイの駆け引きが強まりました。勝利条件が状況型で用意されているため、無駄な交戦を避けるか殲滅を選ぶか、その場の地形・敵編成・目的に応じた判断が常に問われます。
倫理と行動が結びつく“称号システム”

『EOJ』のリブラ値は、敵撃破の抑制や任務達成の姿勢によってLAWからCHAOSへ連続的に揺れ動き、部隊の称号、加入・離脱する仲間、細部の展開、そしてエンディング分岐にまで影響します。無益な殺生を避ける戦い方か、破壊をいとわない強硬策かという選択が、そのまま部隊の顔ぶれや物語の色合いを変えていく仕組みです。ヒーラーや魔術師と縁を結ぶのか、荒事に長けた戦力を招くのか、戦力構成そのものが倫理選好の結果として現れます。続く『WSP』では称号の意味合いがOPMに紐づく評価へと変化し、分岐性は薄まる一方、資源の使い方と作戦効率の指標として機能します。シリーズを通じて、「どう戦うか」が「どんな部隊になるか」に直結する点が核となっています。
資源・兵装・負傷管理が生む“指揮官のジレンマ”

続編『WSP』では金銭の概念が退き、OPMという部隊ポイントで兵装選択や支給品をまかなう設計になりました。高性能の兵装ほど消費も大きく、出撃ごとに役割とコストの最適解を探す必要があります。ユニットは兵装でステータスから移動タイプ、必殺や支援まで丸ごと変わり、同じキャラクターでも作戦ごとに別人のような働きを見せます。負傷度合いによる出撃可否や能力低下、部隊待機でのOPM消費など、短期の勝利と中期の戦力維持のバランスが常にせめぎ合います。『EOJ』の救出任務は称号の揺れとも結びつき、救出で戦闘が増えれば混沌に傾く可能性も生まれます。資源、兵装、負傷、称号が連鎖し、最適解がひとつに定まらない状態こそ、シリーズが投げかける指揮官的思考の醍醐味です。
キャラクターと演出が紡ぐ“続く歴史と手触り”
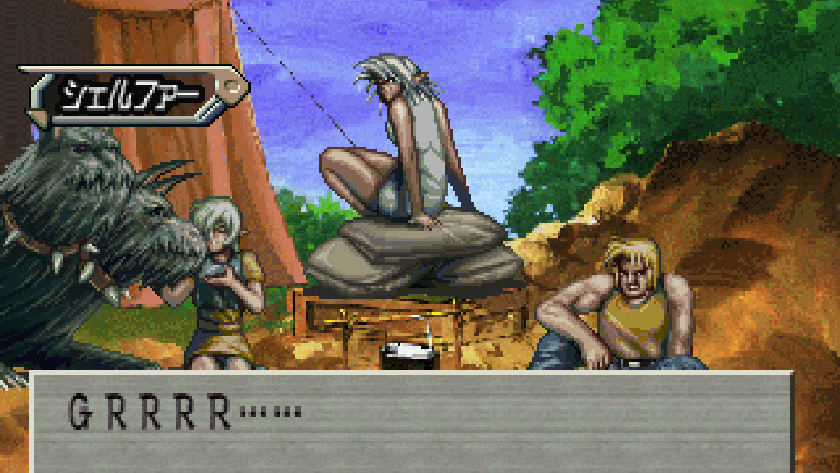
ブライアンとアインを中心に、フォックスリングのドーラ、竜人のバルテュークス親子、アームドウィングのトビカゲ、解放軍の軍師コウメイ、四提督や自律型兵器コロッサスなど、多彩な人物像が戦場と政治の両面で交錯します。『WSP』では前作キャラが立場を変えて再登場し、部隊「ホワイト=サージ」では騎乗・魔装・重装・後方支援など役割が明確に分かれ、章頭ナレーションや一枚絵、ボイスによって場面ごとの温度が伝わります。『EOJ』のリメイクでは必殺技や台詞が増え、戦闘アニメは通常攻撃から被弾まで丁寧に描かれ、アイテムの視認性も高く、操作の手触りが演出と噛み合っています。革命から内乱へと続く歴史は完結しておらず、ファントムゾーンや種族間のひずみ、帝国の権力構造など、未解決の要素が次章を期待させる余韻となって残ります。シリーズ全体で積み上がる因縁と世界の拡張が、周回や続編への想像を自然にかき立てます。
シリーズの一覧
フェーダ ジ・エンブレム・オブ・ジャスティス
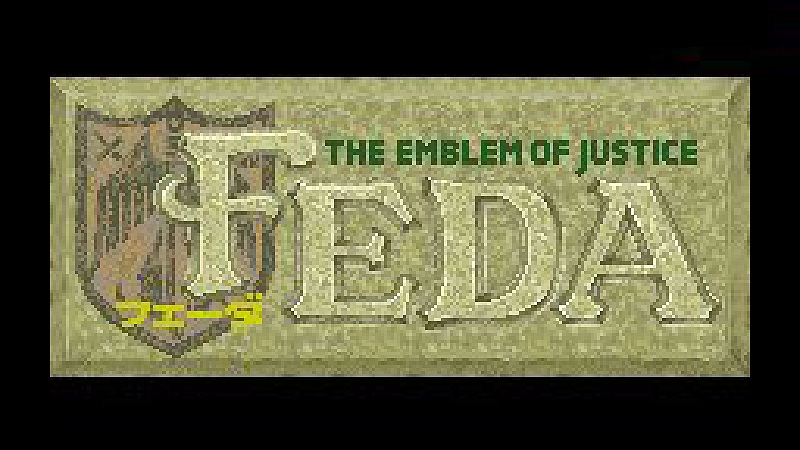
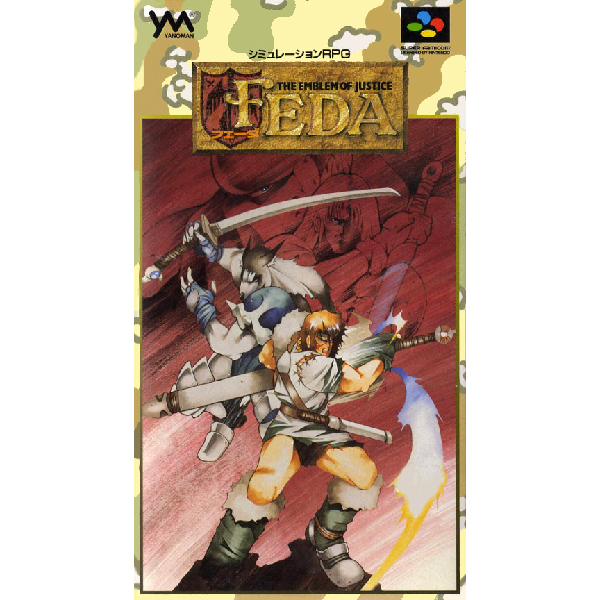
舞台は、千年戦争「ミレニアム・ナイトメア」が終結した後のスクーデリア大陸です。帝国治安部隊の将校ブライアン・ステルバートは、作戦中の虐殺行為に抗し、少女を救おうとして上官へ反撃した結果、投獄されます。獄中でウルフリングの戦士アイン・マクドガル、フォックスリングのドーラ・システィールと出会い、脱獄ののち反帝国組織アルカディア解放軍に合流します。以後、バルフォモーリア帝国総督コバルト・アクセレイセスの圧政に抗い、各地でゲリラ戦・奪還戦・護衛戦など多様な作戦を重ね、スクーデリアの未来を賭けた戦いに身を投じていきます。

ゲームの骨格は、キャンプで編成・装備を整え、ミッションへ出撃し、目的達成後に帰還して次の指令に備える流れです。大きな特徴が「称号」と呼ばれる評価で、部隊が蓄積する「リブラ値」によってLAW寄りからCHAOS寄りまで段階的に変化します。敵撃破数を抑え、目的を必要最小限で果たすと秩序的(LAW)と見なされ、闘いを拡大すれば混沌(CHAOS)に傾きます。この指標は部隊の呼称だけにとどまらず、加入・離脱する仲間、シナリオの細部、最終エンディング(4種類)にまで影響します。例えば、癒やし手のエリスや魔法使いのエルなどはLAW側で参加しやすく、破戒僧リョウカンや砂漠神殿の守護者ティータといった顔ぶれはCHAOS寄りで縁が生まれやすい、といった具合です。

戦闘面では、主人公かパートナーが倒れるとゲームオーバーですが、一般の味方は戦闘不能になっても「捕虜収容所」に送られるだけで、後から救出作戦を実施すれば復帰できます。救出は強制ではなく、キャンプから任意のタイミングで挑め、遅延ペナルティも基本的にありません。多彩な種族が登場するのも本作の味わいで、狼系のウルフリング、鳥人のクラナス、竜人のドラゴニュート、単眼の魔術師グルナレイム、機械種マシンヘッド、ケンタウロスのセントール、亜人アルシデア、昆虫を思わせるアームドウィングなど、それぞれ戦闘傾向や価値観が異なります。世界観は魔法からハイテクまで束ねられ、コバルト配下の四提督や自律型兵器コロッサスといった強敵との対峙を通して、帝国政治と種族間対立の構図が浮かび上がります。

一方で、戦闘アニメのスキップができず長期戦になりがちなテンポ、セーブ枠の少なさ、武器バランス(弓の更新の遅さなど)や一部必殺技の挙動といった粗も指摘されています。とはいえ、行動ごとに精密なアニメ表現が入り、戦闘後は全員に経験値が均等配分されるため育成が滞りにくい作りで、称号システムによる周回の楽しみも支えとなっています。
フェーダ・リメイク! エンブレム・オブ・ジャスティス
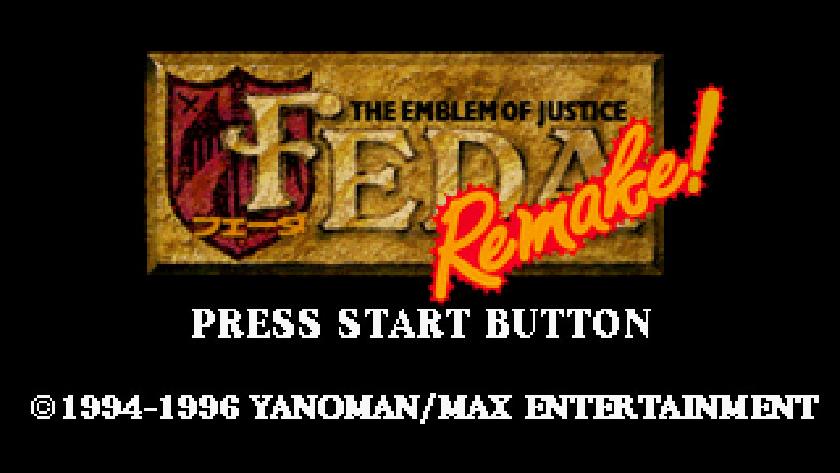

初代の流れを保ちつつ、演出や必殺技、台詞の充実が図られた移植です。アニメパートの挿入、ブライアンの「ガイアストライク」やアインの「峰打ち」などの追加要素、仲間技の再調整が行われ、SFC版で未実装扱いだった技のフォローも見られます。登場キャラクターの加入条件や演出が磨かれ、システム面は原作準拠のまま、救出・称号・仲間の出入りといった骨子が生きています。戦闘テンポやアニメ品質の好みは分かれるものの、ストーリー理解や演出強化という面で初代の補強版に位置づけられます。
フェーダ2 ホワイト=サージ・ザ・プラトゥーン
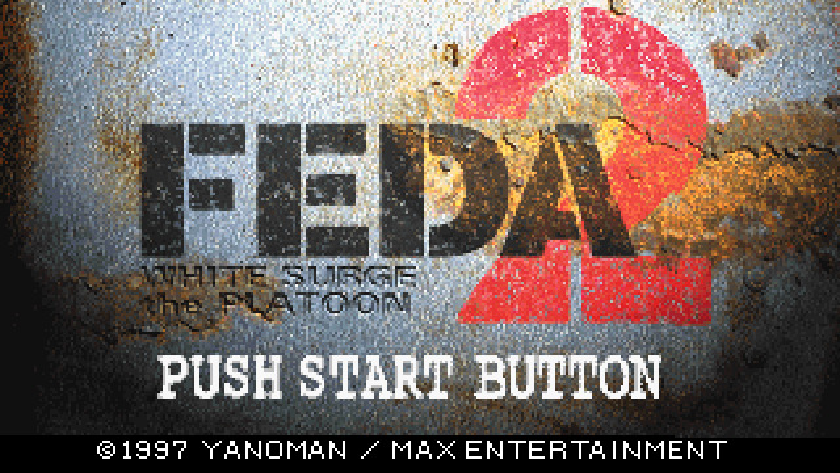

前作の革命から8年、独立を果たしたアルカディア共和国は東西に分裂し内乱状態にあります。帝国側は各地の自治要求に軍駐留を強制する法令で応じ、ドラゴニュートとグルナレイムの間にも軋轢が生じます。東アルカディアは帝国寄りの立場から、主人公ハーベイ・ウィンストン率いる部隊「ホワイト=サージ」をビルガンテス公国へ派遣し、事態はさらに複雑化していきます。前作のアインやトビカゲ、トムらも顔を見せ、バート・バルテュークスやM2・ブラッドレー、レイスなどの勢力が絡み、前作で味方だった人物が立場を変えて対峙する局面も描かれます。
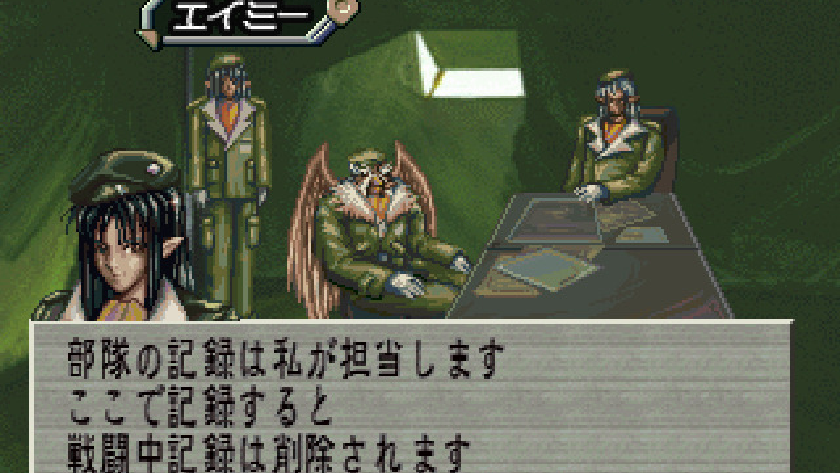
ゲーム面では、3Dポリゴン化した戦場に合わせて操作感が変化し、行動後の再移動(残移動距離の消化)が可能となってヒット&アウェイの戦術幅が広がります。称号はOPMという「部隊ポイント」に連動するスコア的な意味合いに変わり、メンバーは固定化されます。戦闘で倒れた味方は「野戦病院」へ搬送され、軽傷・重傷の段階で出撃可否や能力低下、完治待機の判断が発生します。待機を選べばOPMを消費するため、時間管理とリスク許容の駆け引きが加わります。金銭の概念はほぼ姿を消し、兵装選択や支給品、出撃構成をOPMでやりくりする資源管理が主軸になります。

各ユニットには「兵装」が複数用意され、攻撃・支援・機動力・移動タイプまで総合的に変化します。ハーベイは汎用型で兵装切替により役割を変え、シンシアは攻撃魔装兵と看護魔装兵を使い分け、デバイスは後方火力から拠点防衛まで幅広く、ミネルバは騎乗・非騎乗で戦法が一変します。アインは一騎当千の「侍」特化で突出した切れ味を見せます。レベル制はランク制へ改められ、戦闘後の功績配分でランクが上がり、新技を習得する流れです。勝利条件にも護衛や一定ターンの持久、防衛などが加わり、BGMやナレーション、一枚絵の演出が物語を後押しします。
一方で、カメラの見づらさやイベント時の視点固定、戦闘のレスポンス、ラストバトル専用曲の不在など演出・UI面の粗は残ります。称号が実質スコア化して分岐性が薄まったことも賛否が分かれますが、野戦病院や兵装、OPM管理といった新機軸は戦術面の層を確実に厚くしています。
まとめ

「フェーダ」シリーズは、種族が織りなす歴史と政治、現場判断を迫る作戦設計、そして称号や資源管理でプレイスタイルが色づく設計によって、当時のシミュレーションRPGでも独自の存在感を示しました。初代は倫理と分岐で物語体験を厚くし、リメイクは演出と手触りを補強し、続編は兵装・野戦病院・OPMで戦術と資源の駆け引きを拡張しました。細部の粗やテンポの重さはあるものの、救出や分岐、固定メンバーのドラマ、章頭ナレーションなど、長所は今なお鮮烈です。物語は未完のまま停滞していますが、ファントムゾーンや種族間の亀裂、過去作の因縁が積み上げた伏線は、続編への期待を保ち続けています。シリーズの魅力は、戦場の一手が物語の重さと地続きであるところにあります。遊び方がそのまま歴史の色を変える――それこそが「フェーダ」の本質です。
フェーダシリーズのゲーム一覧